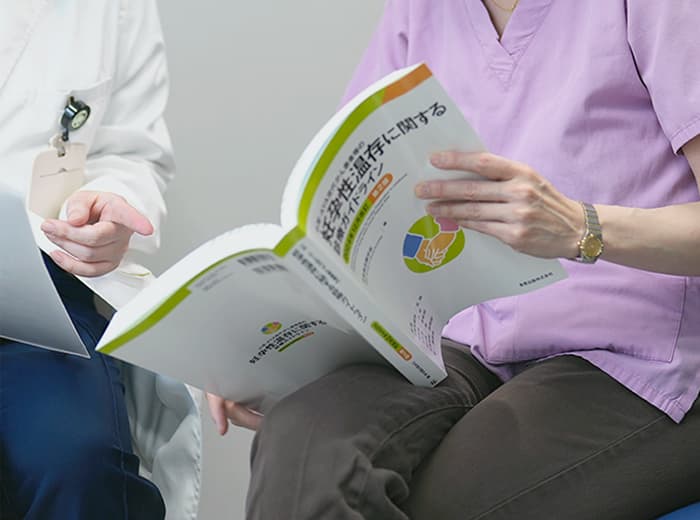婦人科悪性腫瘍
子宮頸がん
子宮がんは、子宮体部にできる「子宮体がん」と、子宮頸部にできる「子宮頸がん」に分類されます。「子宮頸がん」は、子宮の入り口の子宮頸部と呼ばれる部分から発生します。子宮の入り口付近に発生することが多いので、出血などの症状が早い段階で出現したり、婦人科の診察で観察や検査がしやすく、発見されやすいがんです。また、早期に発見すれば比較的治療しやすく予後のよいがんですが、進行すると治療が難しいことから、早期発見が極めて重要です。国内では、毎年約11,000人の女性が子宮頸がんにかかり、約3,000人が死亡しており、また近年、患者数も死亡率も増加しています。当院で行っている子宮頸がんの治療法についてご説明します。
手術療法
前がん病変の高度異形成や上皮内がんと、I~II期の子宮頸がんに対する有効な治療法が手術です。がんの広がりにより子宮頸部または子宮全部を切除します。子宮温存手術(妊よう性温存治療を参照)には、円錐切除や子宮頸部広汎全摘術があります。子宮全摘術には、単純子宮全摘術、準広汎子宮全摘術、広汎子宮全摘術の3種類があり、切除範囲が徐々に広くなります。また、子宮頸がんに対する腹腔鏡下手術も保険適用になっていますが、実施可能な病院は限られています。当院でも施行可能ですが、適応についてはお一人お一人慎重に検討させていただいておりますのでご相談ください。
放射線治療
放射線治療は手術、薬物療法などと並んで、がんに対する主な治療法の1つです。子宮頸がんに対しては、骨盤の外から照射する外照射と、直接子宮頸部のがんに照射する腔内照射、また、放射線を出す物質をがん組織やその周辺組織内に直接挿入して行う組織内照射があります。子宮頸がんでは、病期にかかわらず放射線治療を行うことができますが、比較的進行したがんの場合には、抗がん剤とともに放射線治療を行うこと(化学放射線療法)が多くなっています。また術後再発リスクの高い人や、初回治療で放射線治療を行わなかった人の再発の際の治療手段にもなります。
薬物療法
〈化学療法〉
子宮頸がんに対しては、白金製剤のみによる治療と他の薬を併用する治療が行われています。また、放射線治療の効果を高めるために白金製剤が使われることがあります。子宮頸がんで使う主な白金製剤に、シスプラチン、カルボプラチン、ネダプラチンがあります。白金製剤以外の薬には、パクリタキセル、イリノテカン、ノギテカンなどがあります。点滴や内服などの投与方法が用いられ、使用する抗がん剤はその状況に応じて選択されます。
〈分子標的薬〉
分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わるタンパク質を標的にしてがんを攻撃する薬です。進行・再発子宮頸がんに対して、ベバシズマブが用いられ、抗がん剤とともに使うことによって、治療成績の向上が期待されています。
〈免疫チックポイント阻害剤〉
ウイルスや細菌などの異物に対する防御反応である免疫は、がん細胞に対してもはたらきかけます。がん細胞は自身が増殖するために、免疫の一員であるT細胞に攻撃のブレーキをかける信号を送ることがわかってきました。がん細胞は免疫の機能にブレーキをかける仕組みを使って、T細胞の攻撃から逃れています。ブレーキをかける信号は、がん細胞表面にあるPD-L1というたんぱく質がT細胞表面のPD-1というたんぱく質と結合することにより発信されます。子宮頸がんでは、ペムブロリズマブとよばれる免疫チェックポイント阻害薬を進行子宮頸がんや再発子宮頸がんに対して使用しています。T細胞のPD-1に結合することにより、がん細胞からT細胞に送られているブレーキをかける信号を遮断することで、T細胞が活性化され、抗がん作用が発揮されると考えられています。
妊孕性温存治療
前がん病変からIB1期までの方で将来子どもをもつことを希望している場合には、妊孕性温存治療(妊娠するための力を保つ治療)が可能かどうか、治療開始前に担当医に相談してみましょう。がんの性質や大きさなど一定の基準を満たしている場合、前がん病変からIA1期までは子宮頸部円錐切除術、IA2~IB1期までは広汎子宮頸部摘出術を行い、妊娠する機能を残しつつ治療を行うことが可能です。しかし、治療後に妊娠した場合に早産する率が高くなったり、子宮の入り口が狭くなって月経血が外にでにくくなったり、妊娠しにくくなる可能性があるため、子宮頸がんの手術治療が将来の妊娠に与える影響についても、確認しましょう。
子宮体がん
子宮体がんは子宮体部に発生するがんで、子宮内膜に発生する子宮内膜癌と子宮筋に発生する子宮肉腫の大きく2つに分類されます。実際には95%以上は子宮内膜癌であるため、一般的に子宮体がんと言えば子宮内膜癌を指しています。
手術療法
子宮体癌の手術は病変の治療的摘出と同時に腫瘍の広がり(進行期:ステージ)を診断する目的で行います。子宮全摘+付属器(卵巣・卵管)切除+骨盤(~傍大動脈)リンパ節郭清+腹腔洗浄細胞診が標準的な手術となります。摘出したものを十分に検査し、最終的な腫瘍の広がりを診断し、手術後の追加治療を検討します。癌が明らかに広がっていて全部摘出できない場合や、子宮筋層に広がっていない初期の癌の場合には、手術を縮小して子宮と卵巣・卵管のみ摘出する場合もあります。遠隔転移を認める等、明らかに進行していると手術できない場合もあります。手術のアプローチとして、術前Stageが推定でIA期の類内膜癌異型度(グレード)1-2に対して、腹腔鏡下手術を行っています。また、症例により腹腔鏡下での傍大動脈リンパ節郭清も実施しています。術前Stageが推定でIB期以上の方には開腹手術を行っています。
化学療法
手術の際に癌が子宮の外へ広がっていることが確認された場合や、癌がかなり進行しており手術では対応しきれない場合に使用します。化学療法はすべて点滴治療となります。使用する薬剤はその状況に応じて選択されます。具体的にはTC療法(パクリタキセル+カルボプラチン)もしくはAP療法(アドリアマイシン+シスプラチン)が標準的な治療選択肢として挙げられます。全身状態や副作用などを考慮して、患者さんに合わせて治療を選択していきます。最近では切除不能であった進行子宮体癌や再発子宮体癌にTC療法にペムブロリズマブやデュルバルマブを併用する治療を行っています。「がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌」に対して、ペムブロリズマブが保険適応となっており、子宮体癌患者さんにおいても投与適応があるかどうか(MSI-Highかどうか)については腫瘍組織を用いて調べることができます。また、再発子宮体癌についてはレンバチニブ+ペムブロリズマブを併用した治療も行っており、患者さんの状態に応じて適切な治療を提供していきます。
妊孕性温存治療
子宮体癌の前癌病変とされる子宮内膜異型増殖症(以下、異型増殖症)の方、または子宮体癌のIA期のうち、画像検査上子宮の体部の粘膜内に癌が限局しており、かつ高分化型(グレード1、G1)である患者さんで、妊孕性温存を強く希望される方には、標準治療である子宮摘出という手術療法以外に、高用量黄体ホルモン療法という保存的な治療法も選択肢のひとつであることも説明しています。事前検査として、MRI、CT、子宮鏡検査、子宮内膜組織診、子宮内膜細胞診、凝固系・肝機能血液検査などを受けていただく必要があります。治療内容は高用量の黄体ホルモンを1日2-3回内服していただくことですが、この治療中は治療開始時と終了前には子宮内膜全面掻爬を行います。また1か月に1回外来で超音波、内膜組織診・細胞診検査で治療効果を確認するとともに、問診や血液検査で副作用を確認します。
卵巣がん
卵巣がんは、早期に発見されにくい疾患の一つと言われています。もちろん早期がんで見つかることもありますが、「播種」といって、卵巣の表面から腹膜に拡がっていき、腹水や胸水がたまってきたところで気づかれることも多い疾患です。ただ、適切な治療を行うことで多くの方が治療効果を実感できる疾患でもあります。当院で行っている卵巣がんの治療法についてご説明します。
手術療法
卵巣がんの治療において、最も重要な治療の一つが手術です。手術では、がん組織をできる限り取り除くことが目標です。多くの場合、卵巣だけでなく、子宮やリンパ節も摘出します。また、周辺の臓器も一緒に切除することもあります。このような手術は、最初に行われることもありますが、化学療法を行い、腫瘍をある程度縮小させてから行われることもあります。当院では、がんの広がり、予想される化学療法の効果、手術に対する体の負担なども考慮しつつ、標準治療を順守しながらも患者さんの状態に合わせた治療を考えていきます。
化学療法
手術と並行して行われるのが化学療法(抗がん剤治療)です。多くの場合、手術と化学療法を組み合わせて治療を進めていきます。多くはプラチナ製剤とタキサン系の抗がん薬を使用しますが、患者さんの状態や進行期によって投与方法を変更したり、分子標的薬といった新しい治療薬も組み合わせながら、治療計画を立てていきます。
妊孕性温存治療
若年のかたで、妊孕性の温存(子宮・片側卵巣の温存)を希望される患者さんに対しては、適応を満たせば妊孕性温存手術を実施します。その場合は、初回手術でまず片側卵巣、卵管および大網の一部を摘出(場合によってはリンパ節生検及び腹膜生検)し、永久病理組織検査の結果によって方針を決定します。妊孕性温存手術の適応となるのは、再発のリスクが低いとされる、高分化型腺癌のIA期、境界悪性卵巣腫瘍、胚細胞腫瘍などの患者さんですが、エビデンスやガイドラインに従い、適応を厳密に見極めたうえで判断していきます。
予防的卵巣卵管
切除術について
遺伝性乳がん卵巣がん症候群と診断されているかたが適応となります。年齢やライフスタイルなどを考慮しながら、適切な時期に行うことをお勧めしています。腹腔鏡でほとんど傷が目立たない方法で行います。